富家孝講師の略歴は上部の「プロフィール」をクリックしてください。
「富家孝著・SB新書「死に方」格差社会より}
第8章 「死に方格差」を乗り切るには?
おわりに
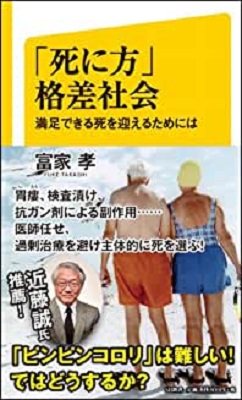 これまで私は、60ほどの本を出してきた。いま振り返ってみると、それらの本はそのときどきの世の中と医療のあり方と大きく関係していた。
これまで私は、60ほどの本を出してきた。いま振り返ってみると、それらの本はそのときどきの世の中と医療のあり方と大きく関係していた。
たとえば、医療過誤事件がメディアで大きく報道されていたときは、医療過誤がをぜ起 こるのか?ということをテーマに本を書いた。医者に対する国民の不満が高まりだした ときは、恵方の医者選びが問違っていることをテーマに本を書いた。
そして、今回、暫して初めて「死」をテーマにして書いてみた、これはやはり、日本が高齢化社会になつてしまつたこと、私自身も高齢者の仲間入りをしたためである。
現在、日本人は年間で約125万人が死んでいる。年間死亡者数は、1966年は約67万人だったから、その倍以上の人が1年間で死んでいる。そして、今後も死亡者数は増え続け、2030年には約230万人になると言われている。
死亡者数の増加も問題だが、私たち個人にとっての問題は、何歳で死ぬかである。これは平均寿命を見れば想像できるが、統計によると年間死亡者数の約3分の2が75歳以上となっている。つまり、いまの時代は人生75年として、生きてゆかねばならないのだ。
この75年間というライフタイムが長いかどうかは、個人の考え方次第だが、75歳を超えたら私たちは否応なしに 「死」を意識しなければならないということになる。
では、どうやって死んだらいいのだろうか?どうやったら幸せに死んでいけるのだろうか?
本書では、このことを、今後の社会のあり方、最先端の情報をもとにして描いてみた。
不備の点も多いと思うが、ご自身の今後を考える際に参考にしていただければ、筆者として幸いである。
なお、本書を執筆するに際しては多くの方の協力をえた。
まず、推薦をしていただいた近藤誠医師にお礼を述べたい。続いて、本書の元になる連載記事「死に方事典」(夕刊フジ) の担当者の幾田進氏にもお礼を述べたいけ また、執筆に協力してくれたジャーナリストの山田順氏、DTP制作にあたってくれた川端光明氏、編集担当のSBクリエイティブの依田弘作氏に感謝したい。
さらに、いつも私を享えてくれる私の家族に感謝したい。そして、読者の皆様の健康と長寿を祈って、筆をおきたい。
富家 孝
 著者略歴
著者略歴
富家 孝[ふけ・たかし]
医師兼ジャーナリスト。1947年、大阪刷ヒ河内郡(現鶴見区)に生ま
1972年東京慈恵会医科大学卒業。病院経営、日本女子体育大学を経て、早稲田大学講師、青L山学院大学講師歴任。専門は、医療生命科学、スポーツ医学。格闘技通としても有名、慈恵医大相撲部総監督(六段)、(財)「体協」公認スポーツドクター、新日本プロレスコミッションドクター。
主な著書に、『医者しか知らない危険な話』(文春文庫)、『危ないお医者さん』(SB新書)、『病気と闘うな医者と闘え』(光文社)なとこれまで、主に医療関係の著書を60冊以上上梓してきた。
自身は心臓カテーテル療法で冠動脈のステント手術を受け、その後2012年に心臓のバイパス手術を受けている。糖尿病は、生活習慣病であるため歩くことを普段から心がけ、薬飲まずこの病気と付き合っている。
SB新書「死に方」格差社会 満足できる死を迎えるためには
2015年8月25口初版第1刷発行
著者・富家 孝
発行者:小川淳 ヨ
発行所:SBクリエイティブ株式会社

 日本消費者協会が調査した「葬儀についてのアンケート調査」(2010年度報告書)というのがある。これによると、葬儀一式費用(葬儀社への支払い) の全国平均は約126・7万円。3年前の同調査と比較すると15・6万円減っている。
日本消費者協会が調査した「葬儀についてのアンケート調査」(2010年度報告書)というのがある。これによると、葬儀一式費用(葬儀社への支払い) の全国平均は約126・7万円。3年前の同調査と比較すると15・6万円減っている。 エンディングノートの仕上げは、前記したように 「葬儀指示書」 である。
エンディングノートの仕上げは、前記したように 「葬儀指示書」 である。 それは、病院内で、その患者さんにかかわる医者、栄養士、リハビリ士、薬剤師などの全スタッフが、「この患者さんは退院させても大丈夫だろうか」という話し合いが続くからだ。いわゆる退院支援活動だが、これは結構長引くのである。病院側には、状態の悪い
それは、病院内で、その患者さんにかかわる医者、栄養士、リハビリ士、薬剤師などの全スタッフが、「この患者さんは退院させても大丈夫だろうか」という話し合いが続くからだ。いわゆる退院支援活動だが、これは結構長引くのである。病院側には、状態の悪い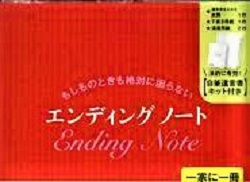 終末治療に対する考え、意思を明確にできたら、次にすべきことは、ご自身の葬儀をどうするか決めておくことだ。そこまでやるのかという声もあるが、最近の 「終括」 では自身の葬儀の仕方まで 「指示書」をつくることを勧めている。
終末治療に対する考え、意思を明確にできたら、次にすべきことは、ご自身の葬儀をどうするか決めておくことだ。そこまでやるのかという声もあるが、最近の 「終括」 では自身の葬儀の仕方まで 「指示書」をつくることを勧めている。 私は、事前指示書は患者さんにとっても大切なものだと思っている。しかし、日本の場合、それは、いくら必要だとわかっていても、をためらうことである。ある調査によると、が「必要」と答えているが、では、それを本当に文書にする場合、抵抗感があるかどうかを訊くと5割以上の人が「ある」と答えている。
私は、事前指示書は患者さんにとっても大切なものだと思っている。しかし、日本の場合、それは、いくら必要だとわかっていても、をためらうことである。ある調査によると、が「必要」と答えているが、では、それを本当に文書にする場合、抵抗感があるかどうかを訊くと5割以上の人が「ある」と答えている。 ただし、ここで降板を発表してからわずか1カ月で逝ってしまった。降板後、すぐに自宅に介護ベッドや点滴器具が運び込まれ、妻のうつみ宮土理さんがかたわらにつきっきりになった。うつみさんは、最期まで、毎朝、ご本人が好きだった山芋と野菜をまぜた健康料理をつくつて食べさせていたという。愛川さんは最期のときまで「さあ、仕事に行こう」と言っていたというが、ご自身の死期を悟ったうえでの言葉だったのではないか。
ただし、ここで降板を発表してからわずか1カ月で逝ってしまった。降板後、すぐに自宅に介護ベッドや点滴器具が運び込まれ、妻のうつみ宮土理さんがかたわらにつきっきりになった。うつみさんは、最期まで、毎朝、ご本人が好きだった山芋と野菜をまぜた健康料理をつくつて食べさせていたという。愛川さんは最期のときまで「さあ、仕事に行こう」と言っていたというが、ご自身の死期を悟ったうえでの言葉だったのではないか。 2015年4月、80歳で亡くなった俳優の愛川欽也さんは、理想的な終末期を過ごしたと言えるのではないだろうか。愛川さんの死に方は、死に方に「いい死に方」と「悪い死に方」があるなら、間違いなくいい死に方だったと思う。
2015年4月、80歳で亡くなった俳優の愛川欽也さんは、理想的な終末期を過ごしたと言えるのではないだろうか。愛川さんの死に方は、死に方に「いい死に方」と「悪い死に方」があるなら、間違いなくいい死に方だったと思う。